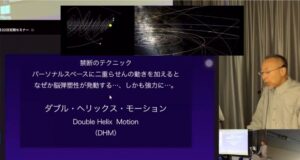【当記事は2015年に執筆した記事で、現在リライト中】
私は運動器プライマリケアの現場において心と痛みの関係を長年にわたって追究してきましたが、どんなに言葉を選んだとしても、ひとたび患者さんのコアビリーフを刺激してしまうと、“次”はないことを学びました。
医療者の側に言葉の選択ミスがなかったとしても、患者自身の無意識に潜んでいる「触れてほしくない何か」にニアミスしたり、思わぬ形で地雷を踏んでしまうと、その瞬間から患者さんの心は施術者から離れていってしまうものなのです。
もっとも…、地雷を踏む危険はメンタル面に潜むデリケートな部分とは限りません。
例えばカーブス大好き主婦の例。肩こりの効果を実感して週4回通い詰めているカーブスにおいて恒例の筋力測定を行った翌朝、トイレの便座から立ち上がろうとした際に腰の激痛、歩行困難に。
脳疲労がぎっくり腰の原因であることを説明したところパート先での対人ストレスーそれも相当に深刻なレベルの問題-を吐露。「メンタル系の話をしても差し支えないタイプなんだ」と安堵し、ぎっくり腰に至った経緯を振り返りつつ痛みの原因を総括しようと「脳疲労を抱えている状態でカーブスでの筋力測定つまり普段より力んで…」と説明した瞬間、間髪入れず「あっ、カーブスは関係ないと思います」と鬼の形相で機先を制せられ…。
カーブス信者と化している本人が「カーブスのせいにされるのだけは嫌だ-無意識に近い深層心理ではカーブスが原因かもしれないと分かっているが、唯一のストレス解消の場であると同時に今の自分の人生にとって最上の生きがい、喜びである対象が皮肉にも強烈な痛みをもたらしてしまったという筋書きは感情的に絶対受け入れられない、認めたくない-」という心理を抱えて来院していることを見抜くことに失敗…。
地雷を軽く踏んでしまった典型例だと言えるでしょう。ちなみにこの患者さんは理学所見と痛みの不一致(乖離現象)-身体の動きが明らかに改善し、それを自覚したにも拘らず喜び感情ゼロ(喜びや安堵を示す“微表情”が現れない)であり、なおかつ痛みも不変-の典型例。
【※微表情…人間の無意識は0.2秒以下の微かな表情変化に現れる。これを利用して真の感情を読み取ることが可能。米国の心理学者ポール・エクマンらによるFACS(Facial Action Coding System、顔動作記述システム)が知られている。トランプのポーカーでの駆け引きやFBIの聴取などでも応用され近年注目を集めている】
で、カーブス主婦の“次”はありませんでした。初診時は些細なニアミスか、軽く踏んだ程度だろうと高を括っていたのですが、次の予約をドタキャンされたとき「軽くじゃなかったな、思いっきり“踏んじゃった”ってことか…。あるいは理学所見と痛みの乖離タイプだったから“脳の自衛措置ど真ん中系”のほうか」と納得。
【※脳の自衛措置…激痛の正体は脳代謝バランスを回復させる目的すなわち偏った血流を是正すべく対照領域の血流を上げようとする言わば代償機能の一種ではないかという私論。脳バランスを乱す源泉(ストレス反応)の湧出が止まらない状況下では脳は自己防衛措置のスイッチをoffにできない(痛みを出し続けざるを得ない)。
この渦中にある患者さんはいかなる治療にも反応しない。治療効果は無意識動作の改善で現認されるが、本人が感じる“痛み”は不変】
おそらく腰椎の捻挫あるいは肉離れや筋膜の損傷等々構造的な原因論すなわちハード論に沿った教科書通りの説明に留めておけば地雷を踏むことはなかったでしょう。
もっとも私が患者だったら「便座から立ち上がる動作で捻挫が…」と説明されたら、意味が分からないと感じますが、聞き慣れて差し障りのない、いかにももっともらしい説明に頷く患者さんのほうが圧倒的に多い。少なくとも私がいるこの地域では…。
ですから地域性を踏まえ、結論としてハード論による説明は安全だと言えます。患者さんの内面に潜む地雷を踏まなくて済むからです。いろいろな意味で無難な方法だと言えます。「痛みの原因はどうでもいいから、とにかくこの痛みを消してくれ」という精神状態にある患者さんのほうが多いからです。とくにぎっくり腰のような激痛状態にあっては。
しかしケースバイケース…。ハード論オンリーでは真に苦しんでいる人、本当に助けなければならない人を救うことはむつかしい。なぜむつかしいと言い切れるのか?
例えばこんな症例-独り暮らしの女性(83歳)。3年前から続いている下肢の激痛と日中の疲労感および明け方の胸痛など。10軒近い病院を受診して脊柱管狭窄の疑いあるいは原因不明と言われ続け…-。
初診当日1時間以上かけて粘り強く詳細な問診をした結果、3年前に受けた24時間ホルダー心電図の解析結果を説明された際、医師から「これ、この部分ね、あと少しここまで上がっていたらあの世行きだったね」と言われ、その日の夜から布団に入ると毎晩のように「明日の朝、私は目を覚ますことができるだろうか」という激しい不安に駆られるように。一連の症状はそのあとから現れてきたことが判明。
激痛を含め様々な体調不良の根源はその不安感にあることを脳科学の知見に照らし合わせて詳しく説明したところ、本人「これまでずっと生きた心地がしない日々だったけれど、ようやく胸のつかえが取れました」と号泣。その2か月後には明るい笑顔で自ら全快宣言され治療終了。
患者さんが10人いれば10通りのドラマが必ずあります。患者さん一人一人と真摯に向き合いさえすれば、都内の有名病院の医師らが10人近く携わっても見出すことができなかった真の原因を問診のみで炙り出すことができるのです。
私はこのような臨床を365日毎日続けています(嘘ではなく本当に年中無休で診療の予約を受けています)。そして先の女性のように患者さん自身あるいはその家族が感涙に咽ぶシーンというものは日常的な光景となっています。
通常の保険診療の現場にあって毎回のように問診に1時間以上かけていたら経営が成り立ちません。ちなみに私は一人の患者さんに2時間近くかけることも珍しくありませんが頂戴する料金は1,500~5,500です。こんなことをしていては家族を養うことなんて…。私には子供がいないのでかろうじて踏ん張れますが。
とは言え、表面に現れにくい目に見えない真の原因を見つけるためには型どおりの問診やカウンセリングでは限界があります。場合によってはどうしても患者さんの内面に深く踏み込む必要が…。先の83歳女性のケースにおいても実は“相当に入り込んで”ようやく心電図ホルダーの一件に辿り着くことができたのです。
ですが、そうした行為は“諸刃の剣”…、素足のまま地雷原に突っ込んでいくようなもの…。
カーブス症例の主婦は最初の型通りの問診に対しては「前日の筋力測定」は伏せていました。しかし、その後もさりげなく続けられた当方のカウンセリングによって思わず露見した事実関係だったのです。型通りの問診と説明だけに留めておけば「絶対に踏むことのない地雷」だったわけです。
こうして私は自業自得のごとき数え切れないほどの地雷を踏み続けてきました。高い授業料を支払い続けてきたのです。
そして今後も払い続けるでしょう。そういう対価を支払っていない、あるいは支払うつもりのない医療者に何をどのように批評されたところでご理解いただけないのは致し方ないこと。そもそも私とは戦っている土俵が違うのですから。