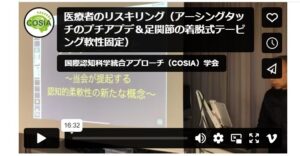「なんかいいな。それ、かっこいいね」
「だろ?前に行ってた接骨院のときはゴツい感じだったけどさ、今度新しくできた○×接骨院に行ったら…。すっごい楽なんだよ、固定してるの忘れるくらい」
「いいなあ、俺も怪我したら、その接骨院に行こお!っと」
これは以前、筆者のところに来た小学生から実際に聞いた話です。そのとき、「ああ、そうか、自分が作った固定装具は意外なところで、意外な宣伝効果をもたらすんだな」と、心底驚いたものです。
小中学生の中にはわんぱく系の目立ちたがり屋さんがいて、ギプス等の固定に対してコスプレとまではいかないにしても、学校公認の目立つアクセサリーを身に着けているような優越感を覚える子がいます。そういう子供は友達に自慢したくなる心性が…。もちろんそれとは反対に目立ちたくないという子供もいるでしょうけど。
また、先日ある女性の患者さんに腱鞘炎の夜間装具(下の画像)を作成したところ…。

その数ヵ月後、その方の夫が同じような症状で来院されました。ご職業は歯科医とのことで、仕事柄、手の痛みは放置できないことは容易に察しがつきます。筆者としても、ふだんより問診に熱が入り…。
いろいろお話を伺う中で、「実は先生が作った妻の(装具)を拝見しまして…、すごいなあと感心しました。接骨の先生の中にもこういうのを作る人がいるんだなと。ああゆうのを見ると、作った人のレベルが分かります」と。どうやら、奥さんの固定装具を見て、こちらにかかる気になったということらしいのです。
以前、筆者が整形の副院長を務めていたとき、近隣の接骨院からレントゲン検査の紹介患者がよく来られました。地域との連携が取れている整形だったこともあり、相当数の接骨院からの紹介患者を見る機会があり、結果的に多種多様な固定装具を見ることに…。
接骨院からの紹介以外にも、他の医療機関で固定されている症例(転医等による)を見る機会もありましたが、総じて接骨院よりも総合病院のような大きな医療機関で施された固定のほうが、プロの目から見て「これはちょっと…」と首を傾げたくなるものが多かったという印象があります。
大規模な医療機関の現場には、柔整のような保存療法のプロがいないので止むを得ないという事情はあるでしょうけれど。
運動器プライマリケアにおけるプロは2種類
整形外科医はあくまでも「外科医」であり、医局で課される訓練のほとんどは手術。すなわち整形は手術のプロ。他方、柔整師は保存療法のプロ。したがって究極的に理想的な運動器プライマリケアというものは、手術のプロと保存療法のプロがタッグを組んで行うチーム医療である。
整形外科医と柔道整復師の水平統合医療モデルにあっては、互いの長所を生かした最高の医療が提供できる。しかし、こうした理念は日本では絶対に受け入れられない。米国であれば受容され得るが、我が国の医療体制はあらゆる次元において、医師の権威が頂点に君臨する封建社会。そのため医師と柔整師が対等の立場で行うチーム医療は「あり得ない」…。
「患者にとって何がベストか」ではなく、「医師にとって何がベストか」、そういう視点で日本の医療は作られている。
欧米と日本の最大の違いは国の成り立ちにあり、日本人のアイデンティティと民主主義とのあいだには埋めがたい溝がある。日本の長い歴史の大半は軍事政権下の社会主義体制であったわけで、たとえば幕府に象徴される武家政治は軍事政権そのものであり、その崩壊プロセスもフランスのように一般民衆が蜂起した革命とは違う。
それはさておき、接骨院が作った固定や装具は、前述したとおり意外なところで意外な人物が見ています。もちろん骨折症例においては、患者が自ら外すような場面は想定されませんので、包帯の下に隠れている固定を家族や友人が見ることはないでしょうけれど、いつどんな形でそれが露見するか分かりません。
例えば、骨折治療中の患者が何らかの理由で突然転医したり、あるいはこれは実際にあった話ですが、とある接骨院でシーネ固定された患者が緊迫包帯により血流障害に陥り、手のしびれとむくみを訴えて別の接骨院に駆け込んだという事例も…。
このように接骨院が提供する固定装具は、いつどこでどのような形で人の目にさらされるか分かりません。患者の状況次第で、家族や友人、さらに不測の転医が生じれば、転医先の医師はもとより放射線技師や看護師など多くの医療従事者に“見られる”ことになります。
柔整師が作成する固定や装具というものは諸刃の剣であり、優れたものを作れば、それは格好の宣伝材料となり得ますが、一方で、拙劣なものを作れば、自院の看板に傷がつくだけでなく、ひいては業界そのものの評判に…。
柔整の多くがレベルの高い固定装具を作るようになれば、周囲の見る目、とくに整形外科医の見る目も変わってくるはずです。そうなれば「整形外科学と接骨医学の融合としての医療現場」、すなわち整形における「PT常勤のリハビリ点数化」と同様に「柔整常勤による“外傷管理”点数化」が実現する未来が待っているかもしれません。
医師が整形を標榜して開業する際、「保存療法のスペシャリストである柔整を常勤させると、外傷管理等における保険点数が加算される」というシステムが導入されたなら、スポーツ障害等のテーピングから軟部組織損傷や骨折・脱臼の処置に至るまで、さらに疼痛管理からロコモ予防プログラムまで、保存療法のほとんどを柔整が担うことで、整形外科医の負担を軽くすることができます。外来における診察、処置の流れも極めてスムースになります。
既に飽和状態の柔整業界にあって、「接骨院の経営は得意でないけれども、技術は持っている」という柔整師の中には、開業せずに生涯勤め上げたいという方もおられます。そういう方々の能力を最大限に発揮できる環境にもなるわけです。
もし厚労省がこれを現実のものにすれば、万が一、柔整の保険業務の道が閉ざされる未来が待ち受けていたとしても、柔整学を後世に残すべく整形外科的保存療法の一部として、学術的地位を担保すると同時に、将来にわたっての存続が可能となります。
例えば、足関節の外傷。なかでも靭帯損傷に対する固定は、その損傷レベルやCRPS(RSD)体質等によって固定形態が自ずと変わってきます。
たとえ軽度の捻挫であってもCRPS(RSD)体質の患者であれば、強い荷重時痛を訴えかねないため、その場合には非荷重の固定措置すなわち松葉杖での通院となり得ます。
その後、徐々に荷重歩行が可となれば、それに合わせて固定の形態を変えていったほうが速やかな回復に繋がります。
最初から荷重歩行を前提にした固定であれば問題ありませんが、そうでない場合、回復レベルに合わせて“歩きやすい固定”に変えていく必要があるわけです。状態が良くなるにつれて患者の活動量も増えると同時に、患者が自ら取り外しできる固定にしてあげることで入浴への配慮も必要になってきます。
つまり外傷に対する固定は、初期において“固定”であっても、回復に合わせて徐々に“機能装具”へと変身させていくプロセスが必要です。
そういう意味において、筆者が行っているプライトンシーネを使った『足関節トランスファンクション(機能遷移)固定』は非常に優れた固定法であると自負しております。受傷直後は非荷重を前提にしたU字固定を作成し、歩行状態の回復に合わせて不要部位をカットすることで形態を変えていくプライトン固定です。

また拘縮の発生と患者の心理状態およびハイブリッドペイン(外傷由来の痛みと脳由来の痛みの混成痛)には明らかな相関性が認められることから、筆者はニューロフィクス(neuro-fixed)という概念を提唱しています。
脳の働きを最大限に考慮して固定法を考えることで、疼痛および腫脹や浮腫のコントロールひいては拘縮発生の予防に寄与する斬新な視点です。以上の理由から、筆者は日々「機能性と美を兼ね備えた固定」を追究しています。
疼痛感受性の亢進している患者にはハードフィクス(シーネ等によるしっかりとした固定)や免荷の適応となる一方、高いレジリエンスを持つ患者の場合、高強度の固定ではなくソフトフィクス(テーピングや包帯等の軟性固定)のほうが速やかな回復に繋がるケースもあります。これについてはこちらのページ「巻き直し不要!着脱式テーピング軟性固定」をご覧ください。.
◇当会が推奨する運動器プライマリケア~機能性固定装具について~
1)筆者が固定装具に機能性と美しさを求める理由
2)ニューロフィクス(neuro-fixed)という視点(復元中)
3)外傷の痛み(ハードペイン)を再考する(復元中)
4)母指3次元固定法(母指球安定型プライトン) (復元中)
5)フィンガートラクション-その意義について- (復元中)
6)膝関節における前面窓式プライトン固定 (復元中)
7)前腕骨骨折における上肢ギプス二重法(前腕部割り入れ併用式)(復元中)
8)足底プライトンシーネ(元ほねつぎの妻が骨折!)(復元中)
9)足関節捻挫におけるf(ファンクショナル)-プライトン固定(復元中)
10)腓腹筋ラッピングシーネ (復元中)
11)体幹プライトンシーネ(元ほねつぎの母が脊椎圧迫骨折???)(復元中)