当会フォーラムは会員サロン(外部サイト)に移設されましたが、トピックの移動ができなかったため、本ページでは旧記事の一部を保存、再現しています。
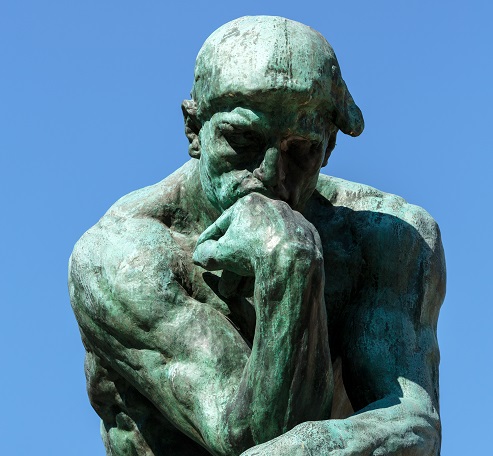
昨日一般の方から、byzouさんトピック内でのコメントに抗議する内容のメールが届きました。
5月3日のコメントにある「画像診断が正しいと信じ込まされている」とはどういうことなのか説明して欲しいというものでした。
「科学的な検査で判明する脊柱管狭窄症という診断のどこが間違っているのか、きちんと説明しなさい」という内容でした。
その批判対象になった文章は以下のとおり。

